コールセンターの通話録音は違法?
開示義務や保存期間の法的ルールとは
UPDATE :

コールセンターの通話録音について「違法性はないのか?」「どのような法的ルールがあるのか?」と疑問を持つ管理者の方は多いでしょう。結論として、通話録音に違法性はありませんが、録音を行う場合は個人情報保護法やガイドラインに準拠した対応が必要となります。
本記事では、通話録音の法的根拠から開示義務・保存期間といった実務上の注意点、さらには導入メリット・デメリット、システム選びのポイントまで、コールセンター運営者が知っておくべき「通話録音に関する知識」を網羅的に解説します。
目次
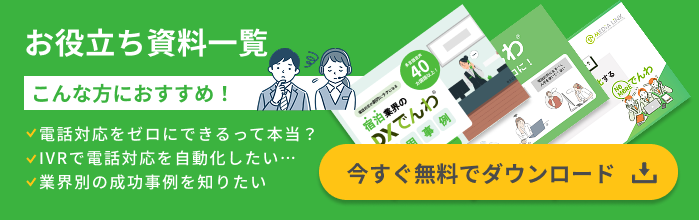
1. コールセンターでの通話録音は違法?
結論から言えば、コールセンターでの通話録音に違法性はありません。また、録音したデータには証拠能力も認められています。
日本では通話録音に違法性はない
日本には通話録音を禁止する法律が存在しません。一方が相手から同意を得ずに録音することを「秘密録音」と言いますが、これを禁止する法律はないため、仮に事前通知なくコールセンターで通話録音を行ったとしても、違法性は低いと言えます。
録音データは裁判でも証拠として認められる
通話録音のデータは法的な証拠能力を持ちます。2000年7月の最高裁判決でも、相手の同意がない録音データの証拠能力が認められています。
▼裁判要旨
詐欺の被害を受けたと考えた者が、相手方の説明内容に不審を抱き、後日の証拠とするため、相手方との会話を録音することは、たとえそれが相手方の同意を得ないで行われたものであっても、違法ではなく、その録音テープの証拠能力は否定されない。
ただし、1977年7月の東京高裁判決では以下のように示されていることから、強制的に/違法な手段で取得した録音データは証拠として認められません。
▼裁判要旨(抜粋)
その証拠が、著しく反社会的な手段を用いて人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法によつて採集されたものであるときは、それ自体違法の評価を受け、その証拠能力を否定されてもやむを得ないものというべきである。
もちろん、コールセンターでの通常業務における通話録音は、こうした問題には該当しません。顧客とのトラブルが発生した際の「言った・言わない」の争いにおいて、録音データは客観的な証拠として活用できます。
2. コールセンターでの通話録音に通知義務はある?
通話録音を行う際、「顧客に事前に告知しなければならないのか?」「法的な義務はあるのか?」といった疑問を持つ方は多いでしょう。新たに録音システムを導入する際は、法的リスクを避けるためにも正確な情報を把握しておくことが重要です。
通話内容に個人情報が含まれる場合は、録音を通知する必要がある
法律上、「録音していることを相手に伝える義務」は存在しません。
ただし、個人情報保護法の第21条で規定されている以下の内容に留意する必要があります。
▼個人情報保護法 第21条
個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
また、日本コンタクトセンター協会が公表している「コールセンター業務倫理ガイドライン」においては、通話録音について以下のように規定されています。
▼コールセンター業務倫理ガイドライン 第2章 7.通話録音情報の保護・開示等(1)
コールセンター業務を行う者は、個人情報である音声を収集し、これらを利用するに当たっては、収集する情報の利用目的をできる限り具体的に特定するとともに、できる限り広く公表するか、または本人に通知しなければならない。
以上の内容を踏まえると、個人を識別できる情報を含む通話を録音する場合、コールセンターは顧客に対して「通話録音を行う旨」と「その利用目的」を通知する必要があると言えます。
録音を通知するアナウンス文例と設定方法
上述したように、通話録音を通知する場合は利用目的を示すことが重要になります。最も一般的なのは「品質向上のために通話を録音させていただきます」というフレーズです。このアナウンスにより、録音の事実と利用目的の両方を簡潔に伝えることができます。
アナウンスの設定方法としては、IVR(自動音声応答システム)を活用するのが一般的です。IVRを利用することで、コールセンターに入電があった時点で顧客に告知アナウンスを自動で流すことができます。
アナウンスする内容のポイントは以下の通りです。
- 録音する事実を明確に伝える
- 利用目的(品質向上、サービス向上など)を具体的に示す
- 簡潔で理解しやすい表現を使用する
なお、以下の記事ではIVRの仕組みや機能、コールセンターに導入するメリットについて解説していますので、詳しく知りたい方はあわせてご覧ください。
3. コールセンターで録音した通話内容に開示義務はある?
特に顧客との間で「言った・言わない」のトラブルが発生した際、「録音された通話内容を聞かせてほしい」といった要求が出されることがあります。こうした場合、コールセンターは録音した通話内容を開示しなければなりません。その根拠となっているのが、「個人情報保護法」と「コールセンター業務倫理ガイドライン」で示されている以下の規定です。
▼個人情報保護法 第33条
本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができる。
▼個人情報保護法 第33条 2項
個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、同項の規定により当該本人が請求した方法(当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法)により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。
▼コールセンター業務倫理ガイドライン 第2章 7.通話録音情報の保護・開示等(2)
コールセンター業務を行う者は、個人情報である音声の開示等の求めに応じる手続を定め、本人の知り得る状態に置いておき、本人より開示等を求められたときは、遅滞なく開示等をしなければならない。
つまり法的にも業界倫理的にも、顧客本人から録音内容の開示請求があった場合、コールセンターは「遅滞なく」録音データを開示する義務があると言えます。
4. コールセンターにおける通話録音データの保存期間はどれくらい?
コールセンターで通話録音を行う場合、「録音データをどのくらいの期間保存すべきか?」「法律で定められた期間はあるのか?」といった点は気になるポイントではないでしょうか。
ここでは、保存期間に関する法的規定と実務的な考え方、そして適切なデータ管理方法について解説します。
法的に定められた保存期間はない
録音データの保存期間については、個人情報保護法にもコールセンター業務倫理ガイドラインにも「○年間保存しなければならない」といった明確な規定が存在しません。
これは各企業が自由に保存期間を設定できることを意味しますが、同時に、実情に応じて適切な期間を設定する責任が企業にあることを示しています。
保存期間の目安はあるのか?
法的規定がない中で、実務ではどの程度の期間が目安とされているのでしょうか。「3年間程度の保存が一般的」という見解も目にしますが、前述したように法的な期間の定めはありません。
保存期間を検討する際は、顧客とのトラブルが訴訟に発展する可能性を考慮し、証拠として必要な期間を想定することが重要です。また、録音データはトラブル発生時だけでなく、スタッフを育成する教材としても活用できることから、可能な限り長期保存することが望ましいでしょう。
一方で、録音データを保存できる容量には限りがあります。そのため、業務の性質やリスクレベル、コスト面などを総合的に勘案し、適切な保存期間を設定することが大切です。
5. コールセンターで通話録音を行うメリット
コールセンターにおいて通話録音システムの導入は一般的であり、業務運営において多くのメリットをもたらします。ここでは、通話録音がもたらす3つの主要なメリットについて解説します。
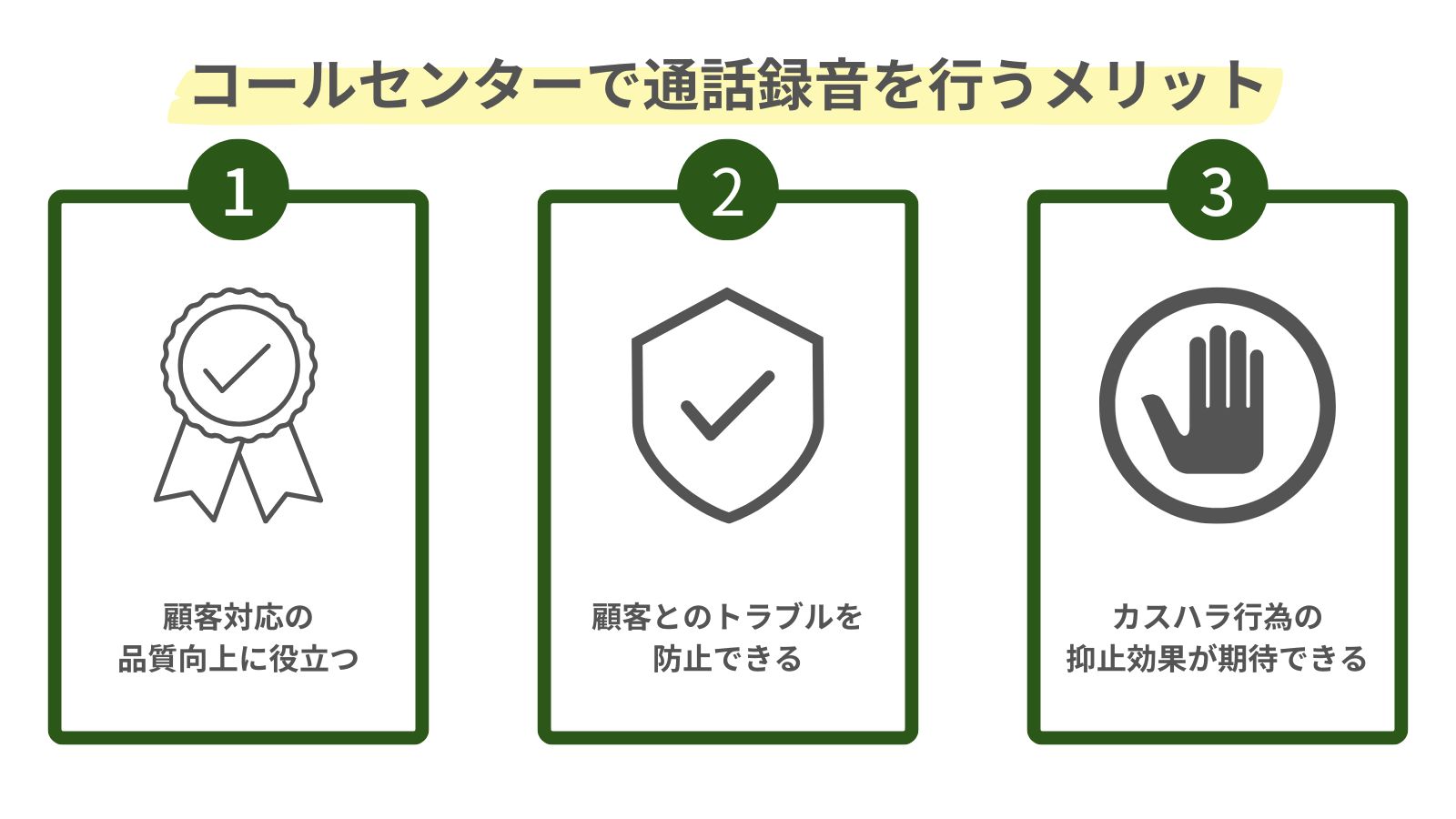
- 顧客対応の品質向上に役立つ
- 顧客とのトラブルを防止できる
- カスハラ行為の抑止効果が期待できる
顧客対応の品質向上に役立つ
録音した通話内容は、オペレーターの育成や応対品質の向上に役立てることができます。例えば、録音データをSV(スーパーバイザー)や教育担当者が分析して改善点をフィードバックすることで、オペレーターの気付きや成長につながります。
また、電話を切ってから顧客と会話した内容を確認できるため、通話中の「聞き間違い」や「メモの取り忘れ」といったミスをカバーすることが可能です。これによって認識違いによる後続業務のミスを防ぐことができ、結果的に企業全体の顧客対応品質の向上につながります。
顧客とのトラブルを防止できる
通話を録音することで、トラブル発生時に「どのようなやり取りが行われたか」をすぐに確認できます。コールセンターでは、電話口で「言った・言わない」の食い違いが発生するケースもよく見られますが、録音データがあれば、どちらの主張が正しいのかを客観的に判断することが可能です。
また、録音データがあれば「トラブルに発展した会話内容」や「クレーム電話の内容」を確認・検証できるため、トラブルやクレームの再発防止にも役立ちます。
カスハラ行為の抑止効果が期待できる
通話録音は、近年問題視されているカスタマーハラスメント(カスハラ)に対する有効な抑止力となり得ます。具体的には、通話開始時に「品質向上のために通話を録音させていただきます」というアナウンスを流すことで悪質なクレーマーを牽制し、迷惑行為を未然に防ぐ効果が期待できます。
また、クレーマーやカスハラ行為者とのやり取りが裁判に発展した場合、録音データを証拠として提出できる点も、コールセンターにとっての大きなメリットです。
加えて、カスハラ行為を受ける可能性のあるオペレーターにとっても、通話録音を行っている事実が精神的な安心感につながります。
なお、以下の記事では「コールセンターで発生するカスハラの実態」と「現場で実践できる対策」について解説しています。詳しく知りたい方は、あわせてご覧ください。
6. コールセンターで通話録音を行うデメリット
通話録音にはメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。導入を検討する際は次の課題を事前に理解し、適切な対策を講じることが重要です。
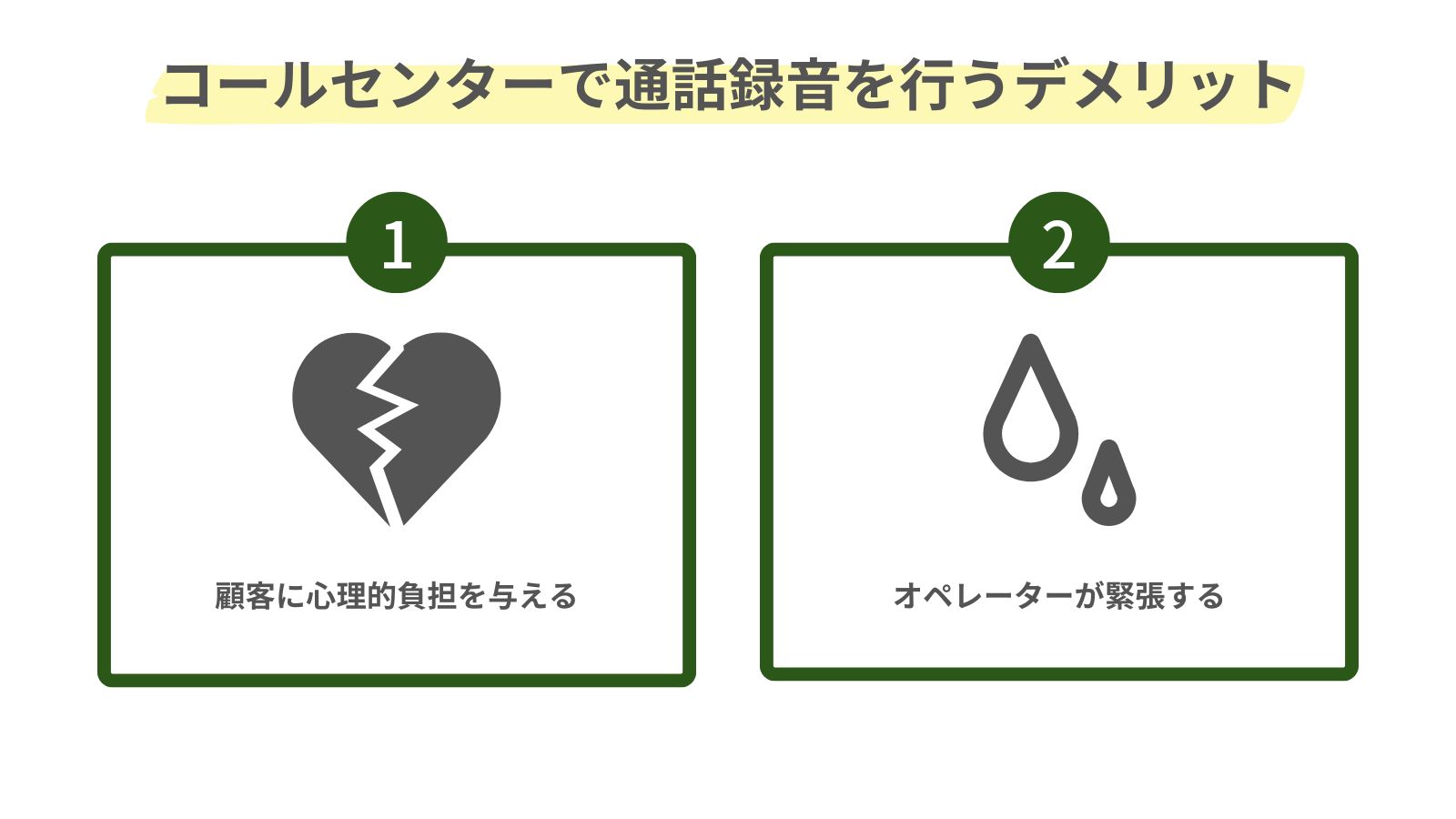
- 顧客に心理的負担を与える
- オペレーターが緊張する
顧客に心理的負担を与える
1つ目のデメリットは、顧客が通話録音に心理的負担を感じてしまう可能性があることです。通話録音の通知を受けることで、言いたいことがうまく伝えられなくなったり、不信感を抱いてしまったりする人もいます。
「自分の発言が録音されて他人の手元に残ることに抵抗がある」「録音内容がどのように利用されるかわからない」といった不安から、人によっては電話を切ってしまう可能性もあります。
このような顧客の離脱を防ぐためにも、「品質向上のため」といった録音の目的を明確にアナウンスすることが重要です。
オペレーターが緊張する
通話録音はクレームやカスハラに対する安心感を与える一方、日々の業務内容を録音されることから、過度に緊張してしまうオペレーターも一定数います。通話内容が評価に影響を与える制度を採用しているコールセンターであれば、なおさらオペレーターがストレスを感じやすい環境にあると言えます。
この問題への対策としては、通話録音の導入目的を全オペレーターに説明することが重要です。以下のような「オペレーター視点でのメリット」を共有し、通話録音に対して納得感を持ってもらいましょう。
- 悪質なクレーム(カスハラ)を防止する効果がある
- 聞き間違いやメモの取り忘れがあっても後からカバーできる
- 自身のスキルアップにつながる
7. コールセンターに導入する通話録音システムの選び方
コールセンターで通話録音を行う方法はいくつかありますが、現在はクラウド型の通話録音システム(または通話録音機能を備えたツール)を導入するのが一般的です。
また、システムを選定する際は単に録音機能の有無ではなく、コールセンターの業務効率化と品質向上を実現するために、以下のような複数のポイントを確認することが重要です。
- 既存システムとの連携性
- AI機能の有無
- セキュリティ機能
- 録音データの保存期間
既存システムとの連携性
新たに通話録音システムを選ぶ際は、現在使用しているシステムとの連携性を確認しましょう。特にCRM(顧客管理システム)と連携できるかどうかで、業務効率は大きく変わります。
SalesforceやZoho、HubSpotなど、お使いのCRMと連携できるシステムを選ぶことで、録音データを顧客情報と紐付けて管理できます。CRMから録音データを再生可能なシステムであれば、顧客対応履歴の確認がより効率化するでしょう。
AI機能の有無
通話を録音するだけでなく、音声のテキスト化や要約文の生成など、AI技術を活用した機能が搭載されているかどうかも重要なチェックポイントです。
通話内容を自動で文字に起こし、要約してくれる機能があれば、通話中にオペレーターがメモを取る手間がなくなります。また、音声を聞かずとも文字で通話内容を確認できるため、社内での情報共有もよりスムーズになります。
セキュリティ機能
録音データには個人情報や機密情報が含まれるため、セキュリティ機能は重要な選定ポイントです。データの暗号化、アクセス権限の設定、操作ログの記録など、データ保護に必要な機能が備わっているかを確認しましょう。
社外の人間がアクセスできないようにするのは当然ですが、特に社内の複数人でシステムを操作する場合は、録音データへのアクセス権限を特定の従業員にだけ付与できるかを確認しましょう。これはデータの不正利用や情報漏えいリスクを低減するための重要なチェックポイントです。
録音データの保存期間と容量
特にクラウド型の通話録音システムを導入する場合は、録音データの保存期間と容量を確認することが重要です。一般的には「保存期間:6カ月」「保存容量:50GB」のように制限が設けられており、サービスによって異なるため、自社が定める保存期間に対応したシステムを選びましょう。
ただし、保存期間が長い/保存容量に合わせてコストが増加するケースもあります。そうした場合は、「音声ファイル」や「音声をテキスト化したCSVファイル」をダウンロードできるシステムを選ぶとよいでしょう。落としたファイルを自社サーバーに格納しておけば、システム上の保存期間の影響を受けずに録音データを保管できます。
なお、クラウド型の通話録音システム以外の固定電話で通話録音を行う方法については以下の記事で解説しています。
8. コールセンターにおすすめの通話録音機能付きシステム
最後に、コールセンターにおすすめの通話録音機能付きシステムを紹介します。新規でコールセンターを構築する場合と、既存のコールセンターに通話録音機能を追加する場合に分けて紹介しますので、自社の状況に応じて参考にしてください。
新たにコールセンターを構築する場合
新規でコールセンターを立ち上げる際は、メディアリンクが提供するオールインワン型コールセンターシステム「MediaCalls」がおすすめです。IP-PBX、CTI、ACD、通話録音など、中~大規模なインバウンド型コールセンターでの業務効率化に必要となる豊富な機能を搭載しています。
通話録音機能については、システムを通して行われたすべての通話(または必要な通話のみ)を録音することが可能です。録音された音声は通話履歴画面から検索、再生、ダウンロードできるため、前述した開示請求への対応や品質向上にも活用できます。
コールセンターの構築から運用まで一貫したサポートを提供しているため、初めてコールセンターを立ち上げる企業にも適しています。
既存のコールセンターに通話録音を導入する場合
既存のコールセンターに通話録音機能を追加する場合や、小規模なコールセンターを構築する場合は、クラウドIVR(自動音声応答システム)サービスの「DXでんわ」がおすすめです。
「DXでんわ」には、電話相手が吹き込んだ用件を自動で録音し、AIが要約して文字に起こす機能が標準搭載されています。また、IVRによって転送されたあとの従業員と顧客の通話内容を自動で録音・テキスト化する機能もあるため、電話中にメモを取る必要もありません。
録音データやテキストはシステムの管理画面から簡単に確認できるため、過去のやり取りを遡って確認したい場合や、社内で情報共有を行いたい場合も便利です。
通話内容を録音するだけでなく、電話業務全体の効率化を図りたい方は、ぜひ以下より「DXでんわ」の詳細をご確認ください。
関連記事

テレマーケティングとコールセンターの違い:連携の重要性を理解しよう!

問い合わせ削減方法10選!件数と工数に分けて解説

IVR(電話自動音声応答システム)とは?メリット・デメリットと導入ポイント

AI電話自動応答サービス比較6選:失敗しない選び方も解説

電話自動応答システムの振り分けで業務効率化!3種類のシステムも解説

会社に通話録音を導入する5つのメリットと4つの手段

電話対応でのカスハラにどう対処する?7つのステップと5つの対策を解説

通話録音をクラウド化するメリットとは?選定ポイントとおすすめシステムも紹介

営業時間外の電話にどう対応する?自動応答で負担をなくそう!








