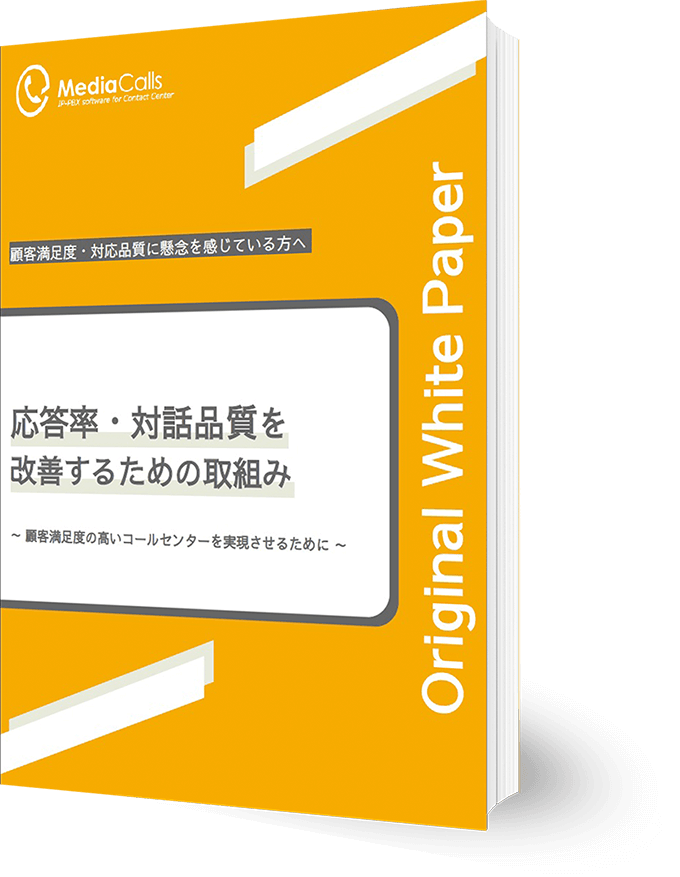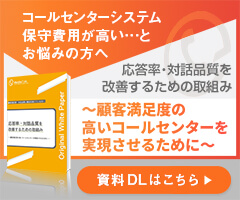コールセンターのクレームの処理を効率的に行うために
知っておきたい対処方法とは
UPDATE :

コールセンターにおけるクレーム処理は、直接的な利益に繋がるものではありません。
しかし、不適切な対応をしてしまっては、顧客満足度を大幅に低下させる可能性もあります。
今回はクレーム処理を効率的に行うための対応方法についてご紹介します。
目次
- 1.コールセンターで発生する3つのクレーム
- コールセンターで発生するクレームの種類①:クレーマー
- コールセンターで発生するクレームの種類②:製品や企業に対する不満など
- コールセンターで発生するクレームの種類③:オペレーターの対応に関するクレーム
- 2.クレーム処理がうまくいかない理由
- KPIとのジレンマ
- オペレーターのスキル不足
- 顧客情報の引き継ぎ不足
- 3.最低限押さえておきたいクレームの対応方法
- 不正確な情報は伝えず、しかし何も伝えられない状態は避ける
- モニタリング・ウィスパリング機能を活用する
- レポートを活用し、正しく現状を把握することで見せかけのKPIに騙されない
- ブラックリストを活用する
- 4.クレーム処理に役立つ機能を搭載する「MediaCalls」
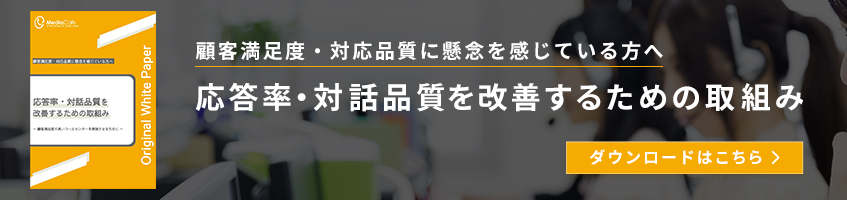
コールセンターで発生する3つのクレーム
各コールセンターによって状況やコール件数は異なりますが、一般的にコールセンターには多種多様な内容の問い合わせが入ってきます。そんな問い合わせの中には一定数いわゆる「クレーム」も含まれています。
顧客はコールセンターのオペレーターと話していると理解していても、企業全体と話している認識を持っています。そのためオペレーターの対応が企業の評価に直結するケースは少なくありません。
そこで今回は、直接的な利益になりづらいクレーム対応を顧客満足度向上のチャンスに変えるため、
コールセンターに寄せられるクレームについて以下の3種類に分けてみていきます。
コールセンターで発生するクレームの種類①:クレーマー
クレームと聞いて最初に思いつくのは、「クレーマー」からの電話です。クレーマーからの問い合わせの中には、製品や企業、コールセンター側に大きな過失がないにも関わらず、発生するケースも少なくありません。
この場合、コールセンター側で対応フローやルールが確立されているか、また、各オペレーターの対応スキルによって、顧客満足度を落とさず解消できるかどうかが決まります。
コールセンターで発生するクレームの種類②:製品や企業に対する不満など
製品の機能不備や説明書及び公式HP上での説明不足、企業の不祥事をはじめとしたトラブルなどに起因するクレームも考えられます。この場合は、製品のリリース時やトラブル発生時に、どれだけ早く対応ルールを構築し、各コールセンターに展開できているかなど、各オペレーターの対応スキルに依存するケースが多いです。
コールセンターで発生するクレームの種類③:オペレーターの対応に関するクレーム
コールセンターに起因するクレームも考えられます。コールセンターに起因するクレームの多くはオペレーターの対応が顧客に不快感や不満を与えてしまうケースも少なくありません。
原因として、各オペレーターの配慮不足やスキル不足なども関係していますが、その他、KPIを意識するあまり対応が疎かになり、別のオペレーターに転送する際に顧客情報を適切に引き継ぎできず、
顧客側で何度も同じ話をしなければならない状況が続いてしまったりすることなどが考えられます。
クレーム処理がうまくいかない理由
クレームについて、大きく3種類に分けて解説しました。それぞれで異なったポイントもありましたが、どの種類にも共通しているのが「KPIとのジレンマ」、「オペレーターのスキル不足」、「顧客情報の引き継ぎ不足」が挙げられます。
以下でそれぞれについて解説します。
KPIとのジレンマ
一般的にコールセンターでは平均処理時間の短縮や、呼損数(放棄呼数)の最小化を通して、多くのコールに対応することが求められます。しかし、「クレーム対応」というシーンにおいては、このKPIや数字への意識がマイナスにつながることは少なくありません。
オペレーターのスキル不足
クレーム処理がうまくいかない理由として、各オペレーターのスキル不足も大きな要因の一つです。
コールセンターは一般的に離職率が高い業界と言われており、熟練度が高まる前に辞めてしまったり、
スキルが十分に身についても、何らかの理由で職を離れたりということが頻繁に起こります。
そのため、各オペレーターのスキル向上や、コールセンター全体として対応レベルを高い水準でキープさせることが困難な状況となっています。
顧客情報の引き継ぎ不足
電話に出たオペレーターでは対応し切れないクレームや内容であった場合、他の担当者に引き継ぐケースなどがありますが、その際に、情報の共有が適切に行われず、顧客が最初から説明し直さなければならない状況になると、より大きなクレームへと発展してしまうなどのリスクが考えられます。
ただ、どれだけ注意していても顧客から一度受けた問い合わせ内容の共有などは、人的ミスが発生しやすいものです。そのため、ラストエージェント機能(前回通話したオペレーターに対し優先して着信させる機能)を用いて問い合わせ内容の伝達ミスを防ぎ担当振り分けを自動化するなどできるところからDX推進を進めることも重要です。
最低限押さえておきたいクレームの対応方法
次に、クレームを適切に処理するためにコールセンター が最低限押さえておきたいポイントや対応方法について解説します。
不正確な情報は伝えず、しかし何も伝えられない状態は避ける
KPIを意識して、早く対応を終えなければと考えているオペレーターなどは、顧客の不満やクレームを早く和らげ、対応を終えようとする意識が働くため、不確定な情報を伝えてしまうこともあります。
KPIにとらわれ過ぎないような体制の構築や、伝えるべき情報をコールセンター内で共有し、正確な情報のみを伝えられるような仕組みづくりが重要となります。
一方で、伝えられる情報が少なくなってしまう可能性も考えられます。情報量が少なく、問題が解消されていないのであれば、顧客としては納得しにくいです。そのため、情報を伝えられる時期や情報が更新される場所(HPなど)を最低限、回答できるようにしていくことが望ましいです。
モニタリング・ウィスパリング機能を活用する
オペレーターのスキル不足を補う方法の一つとして、SV(スーパーバイザー)が顧客対応中のオペレーターの通話をモニタリングしながら、オペレーターのイヤホンにのみ指示やアドバイスができるウィスパリング機能を活用すると良いでしょう。
新型コロナウィルス蔓延に伴い在宅ワークにシフトした方も多い中、クレームが発生した場合のサポートにはモニタリングチェックが重要となります。
レポートを活用し、正しく現状を把握することで見せかけのKPIに騙されない
本記事の最初でも触れたように、各オペレーターがKPIを追求するあまりクレームが増えてしまうというケースはよくみられる例です。
SVをはじめとした管理職の方は、コールセンターの数字を正確に把握し、クレームが増えてしまっている原因やクレーム増加の兆候がないかをチェックしておくことが重要です。
また、運用状況が一目でわかるように正確かつスピーディーなレポーティングを行えるルールづくりや、システム構築は欠かすことはできません。
正しい運用状況を数字で把握し、クレームの原因をあぶりだし対策を打つためにはレポート機能が必須です。
ブラックリストを活用する
クレーマーへの対応として、クレーマーをはじめとした要注意の顧客からの入電については、着信時にわかるようにすることで、対応前に気持ちや体制を整えることができます。
体制面で言えば、要注意の顧客からの電話を対応する場合は、可能な限りSVがモニタリングするなどの対応が考えられます。
また、ブラックリスト(要注意顧客のリスト)を活用することで、経験豊富でスキルの高いオペレーターに振り分けるなどの対応も有効です。
クレーム処理に役立つ機能を搭載する「MediaCalls」
弊社が提供している“クラウド型コールセンターシステムMediaCalls”では、コールセンターに寄せられるあらゆるクレームを適切に処理する機能が準備されております。
どんなオペレーターでもクレームを正しく処理できるようにするために、
- モニタリング・ウィスパリング機能
- 三者通話機能
- 「ブラックリストに登録された顧客からの着信時に警告を表示する」などの操作が可能
- 電話応対中のトラブルを、リアルタイムにレポーティング
など、オペレーターだけでなくSVの業務効率も改善しながらクレーム処理を効率化する機能がそろっております。
さらに自社開発のソリューションのため、他社製品と比べて、圧倒的な低価格でご提供しています。詳細については、以下のリンクよりご覧ください。
関連記事

コールセンターとは?定義や種類、業務内容を解説

コールセンターの応答率向上!改善のカギは「見える化」にあり